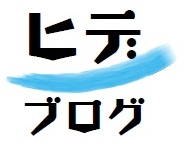みなさん機械部門の技術士を目指す時に、どの科目にするか悩んでいませんか?
今回は、そんな悩みを持っている方向けに記事を書いてみたいと思います。
科目の選び方、考え方は同じなので、機械部門以外の方も参考にしてみてください。
実際に科目を選ぶのは、受験申込書を記載する時だと思います。
ここで適切な科目を選んでいないと、後で苦しい思いをすることになります。
それは口頭試験の時です。
口頭試験で自分の専門ではない観点から回答した時が最悪です。
試験官に専門科目不一致と判断されます。
それは不合格と判定されることです。

そうならないために、自分の専門が何なのかしっかりと考えるよい機会にしましょう。
私も結構悩みました。
機械設計は幅が広いので、いろんな科目を広く浅くやるからです。
それってどれも中途半端ということでしょうか。
そうではないと思います。
どこかに核があるはずです。
どれもこれもやってるけど、一番時間を費やしている業務。
自分が好きな業務、または得意な業務。
ここで、自分の専門が何なのかを探してみましょう。
科目の種類
ここで改めて、機械部門の科目とその内容を見てみましょう。
令和2年度 技術士第二次試験 受験申込み案内 からの引用です。
| 選択科目 | 選択科目の内容 |
|---|---|
| 機械設計 | 設計工学、機械総合、機械要素、設計情報管理、CAD、CAE、PLM、その他の機械設計に関する事項 |
| 材料強度・信頼性 | 材料力学、破壊力学、構造解析・設計、機械材料、表面工学・トライボロジー、安全性・信頼性工学、その他の材料強度・信頼性に関する事項 |
| 機構・ダイナミクス・制御 | 機械力学、制御工学、メカトロニクス、ロボット工学、交通・物流機械、建設機械、情報・精密機器、計測機器、その他のダイナミクス・制御に関する事項 |
| 熱・動力エネルギー機器 | 熱工学、熱交換機、空調機器、冷凍機器、内燃機関、外燃機関、ボイラ、太陽光発電、燃料電池、その他の熱・動力エネルギー機器に関する事項 |
| 流体機器 | 流体工学、流体機器、風力発電、水車、油空圧機器その他の流体機器に関する事項 |
| 加工・生産システム・産業機械 | 加工技術、生産システム、生産設備・産業用ロボット、産業機械、工場計画その他の加工・生産システム・産業機械に関する事項 |
たくさんあります。
私の場合は、マテハンやプロセス設計をするので、
機構・構造設計の他に、材料強度・信頼性や動力計算もします。
ポンプも扱うから流体機器も少しやります。
冷凍機器も選定、配置、配管設計や試運転調整をやります。
加工・生産システムもある程度知っていないと機械設計は無理です。
というわけで、この表だけ見ていると悩みます。
ではどのように選べばよいのでしょうか。
こんな観点から考えてみましょう。
主業務から選ぶ
やはりこれが一番です。
自分が最もやっている業務の科目から選ぶことです。
ここで、みなさん自分がどんな業務をメインにしているかを考えましょう。
図面描き。
動力、強度、性能などの計算。
構想、配置、生産、工程などの全体計画。
積算、コスト検討。
保守、改造、不具合などの対応。
試験、試運転調整。
これらを全部ひとりではできませんよんね。
時間に余裕があればできるかもしれません。
でも今の時代にそんな余裕はありません。
なので分担して業務をすることになります。
みなさんの主業務はどれでしょうか。
私の場合は、機構・構造設計がメインです。
機械要素を駆使して、マテハン装置を設計します。
ワークを運んで、ひっくり返して、上げて下げて、入れたり、出したり、混ぜたり、分けたりなどの機構を考えます。
それらの機構を最適に配置した全体構造を設計します。
詳細設計では材質、部材サイズ、ボルト、アクチュエータ、センサなどの機械要素を全て選定します。
科目の内容に機構・構造設計ってないですが、機械要素が機械設計の中にあります。
なので機械設計が専門科目かなと当時は思いました。
でも、強度計算やCAEの計算モデル構想も結構やります。
信頼性も機械設計の基本なのでやります。
ここで、2つに絞られました。
好きな業務から選ぶ
図面描き、計算、計画などどれも同じくらいやっている方はたくさんおられるでしょう。
じゃあ、その中からを好きな業務の科目を選ぶのがよいでしょう。
好きな業務であれば、嫌いな業務よりいいです。
途中でくじけたり、飽きたりする可能性はないでしょう。
得意業務から選ぶ
たくさんの業務をやっていても好きなものがない場合もあります。
そんな時は得意な業務の科目を選びましょう。
得意とは何でしょうか。
それは他人と比較したり、自分自身の中で考えてみた時、
スピードが速かったり、
精度が高かったり、
ミスがなかったり、少なかったり、
独創的などであったりすれば、
それは得意と言えます。
試験問題から選ぶ
ここが重要です。
絶対に過去の試験問題を見てみて、最終結論を出しましょう。
選択した科目は専門分野になるので、
非常に深い内容を問われることになります。
試験問題を見て、すぐに解答内容が思い受けぶのであれば、
それはあなたの専門科目であると言えます。
というか、その段階で解答内容が思い浮かべば、すでに技術士レベルです。
すぐに申し込みましょう。
以下に令和元年と2年の試験問題にある各科目別のキーワードを抽出してみました。
これらのキーワードについて、定義、特徴、メリット、デメリット、
動向など600字詰め原稿用紙1枚を埋めるだけの知識を持っていますか。
それだけでなく、それらのキーワードを業務に取り入れているか、
やったことがあるか、または取り入れた場合、どうなるかイメージできるか。
そんな観点で見てみてください。
| 専門科目 | 年度 | 必須科目 キーワード |
|---|---|---|
| 機械部門全般 | R01 | 擦り合わせ手法、組み合わせ手法、SDGs |
| R02 | 技術伝承、持続可能性、省エネルギー社会 |
| 専門科目 | 年度 | 選択科目 キーワード |
|---|---|---|
| 機械設計 | R01 | 品質工学:田口メソッド、パラメータ設計、ロバスト設計、サイズ公差、幾何公差、フェイルセーフ、設計審査、設計検証、設計の妥当性確認、機械要素、介護機器、国際標準化 |
| R02 | 付加製造、積層造形、3Dプリンティング、標準化、溶接継ぎ手、環境配慮設計、3R、コンカレントエンジニアリング、マルチマテリアル設計、MaaS、CAE | |
| 材料強度・信頼性 | R01 | 構造物の力学的挙動予測、炭素繊維強化プラスチック、疲労強度向上表面処理、延性脆性遷移温度 |
| R02 | 溶接継ぎ手の疲労強度、塑性拘束、安全性と信頼性、金属積層造形技術、軽量化、設計寿命 | |
| 機構ダイナミクス・制御 | R01 | PID制御、オイルダンパ、振動検出器、遊星歯車機構、動力制御機械装置 |
| R02 | 固有振動数、ベクトルモード、質量刺激係数、有効質量、能動型動吸振器、ステッピングモータ、ローレンツ力、歯車、騒音低減 | |
| 熱・動力エネルギー機器 | R01 | 冷凍機成績係数:COP、先進超々臨界圧火力発電、窒素酸化物抑制手法、ブレイトンサイクル、再熱ブレイトンサイクル |
| R02 | 蒸気圧縮式冷凍サイクル、理論冷凍成績係数、ヌセルト数、ビオ数、個体燃料の燃焼方式、蒸気タービン効率、再生可能エネルギー、コージェネレーションシステム、分散型エネルギーシステム、木質バイオマス燃料 | |
| 流体機器 | R01 | サージング、シャドーグラフ法、シュリーレン法、マッハツェンダ干渉計、ナビエ・ストークス方程式、レイノルズ方程式、低騒音化、人工知能、再生可能エネルギー |
| R02 | 円柱の抗力係数、PTV、PIV、ナビエ・ストークス方程式、気流体の速度三角形、CFD解析、3Dプリンタ、IOT、ICT | |
| 加工・生産システム・産業機械 | R01 | 工作機械性能基本特性、塑性加工、生産リードタイム、MRP、just in time、IOT、EV |
| R02 | タレットパンチプレス、レーザ加工機、工作機械の運動精度、サイクルタイム、年間生産量、編成効率、画像処理技術、形状計測技術、工程設計、CAD・CAM、3Dプリンタ、BCP |
普通の初心者の技術者は、まったく解答内容が思い浮かばなくて当たり前です。
だから勉強するのです。
でも、試験問題を見たときに、
少なくともあれを勉強すればいいとか、
あの参考書、あの技術資料
またはあの記事や論文に書かれていてたはずと、
ピーンとくるものがあれば、
それはあなたの専門科目になる可能性が大です。
まったく感じるものがなく、
突破口が見当もつかない場合は他の科目にしましょう。
それで勉強を始めても効率が悪く、
時間を無駄にしてしまいます。
まとめ
機械部門及び他部門を目指しているみなさん、
受験する専門科目は慎重に決めましょう。
自分の主にやっている業務は何か。
好きな業務は何か。
得意な業務は何か。
だけど難しく考える必要はありません。
今はどの分野が専門か判断できなくても、自信がなくても、
とりあえず決めてみて、勉強して不足部分を補っていき、
それから改めて専門科目を決めても大丈夫です。
ただし、受験申込期日を意識して、
それまでに決めらるようにしましょう。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。